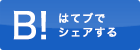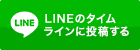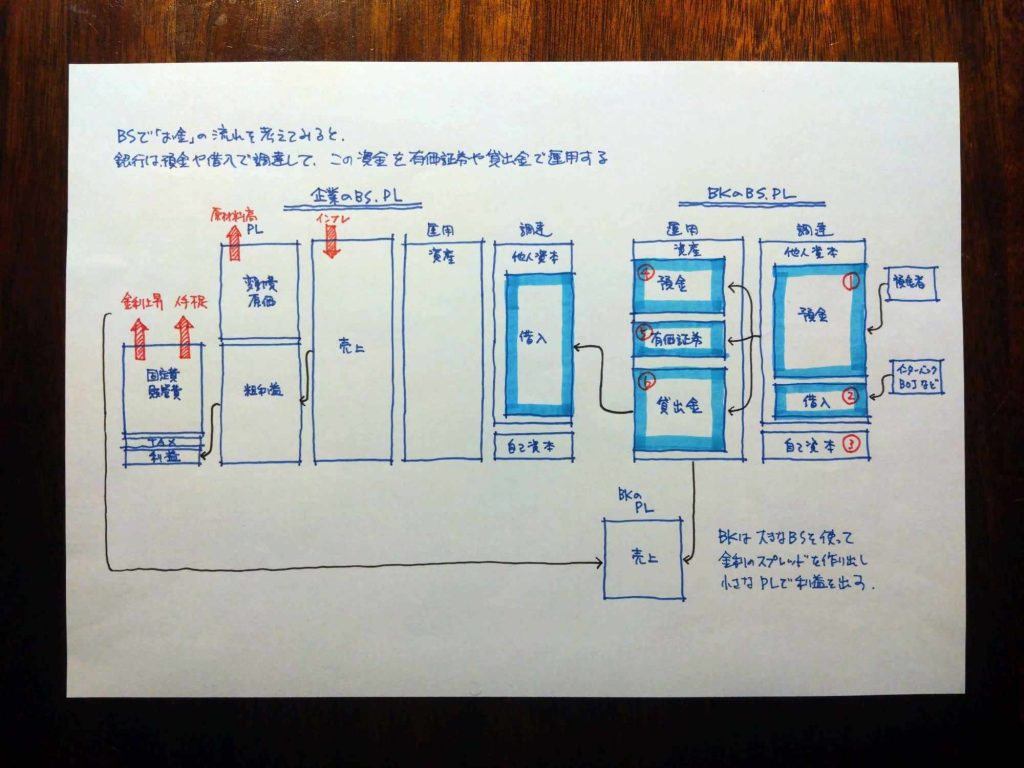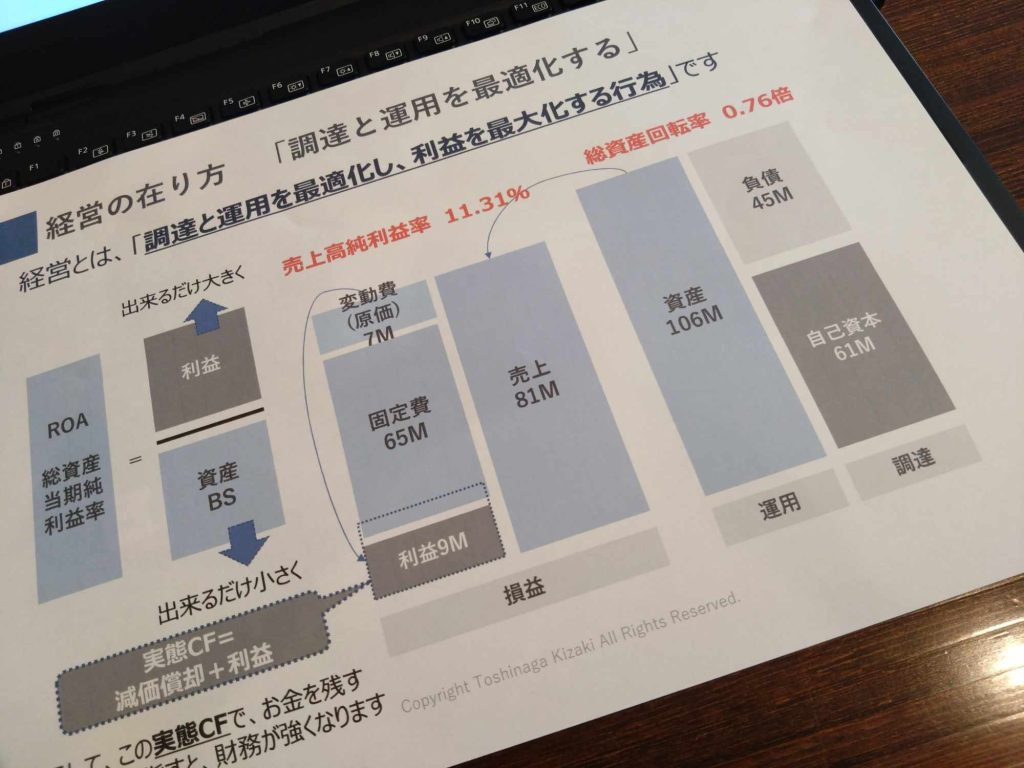皆様、明けましておめでとうございます、本年もよろしくお願い致します。
なかなかブログを書く時間が取れず、発信が出来ていないのですが、自分自身の備忘録のためにも必要なトピックスがありましたので、これについて書き留めてみたいと思います。
具体的には日本銀行による金融政策の変更が、今後の日本経済に何をもたらすのか、という事についての思索と解釈についてとなります。目を通し頂ければ幸いでございます。
年末年始に何名かの経営者の方々と、恒例の電話MTGなどを行っているのですが「賃金」についてのテーマが多く上がった様に思います。
「人手不足が本当に大変、賃上げや採用コストの増大は、本当にもう勘弁して欲しいよ」
経営者の方々との会話で、天候の話と同じぐらいで、こうした言葉を聞くことが増えた気がします。円安もあって原材料費や荷造運賃が上がり、労働人口も減っているので、その上での「賃上げ」要求ですから自然な反応と思います。
でも、もしこれをお読みになられている方が経営者あった場合、この「賃上げ」を一過性のブームや、政府からの「お願い」程度に捉えているとしたら、それは相当に不味いかもしれません。
なぜなら、日本経済における基本的なルールというか、潮目というか、流れというか、経営の前提条件が完全に書き換わったにもかかわらず、古い前提条件や、従来の価値観で、経営をし続けようと思っている事と同じだからです。
さて、日本銀行の植田総裁は12月25日、日本経済団体連合会(経団連)の審議員会で講演をされました。講演内容はすでに日銀のWEBサイトで公開されています。
金融政策が大きく変更されたわけですから、経済環境への影響は待ったなしです。ビジネスパーソンならば、こういった政策変更に伴う発信は一次情報をまずは当たる、といった意識付けはとても大事と考えます。
そしてこういう習慣は、ご自身の仕事にも影響が生ずると思いますし、少し先の未来を予測できることは、とても大事なことではないかと、私自身は考えております。
(この資料、今後の経営の前提条件の変化について示唆に富む内容に溢れておりますので、ぜひダウンロードしてご一読下さい)
賃金上昇を伴った「物価安定の目標」の達成に向けて
日本経済団体連合会審議員会における講演日本銀行WEBサイト https://www.boj.or.jp/about/press/koen_2025/ko251225a.htm
植田総裁がこの講演で語った言葉には、これまでの「期待」や「お願い」とは一線を画す、非常に重い「決意」が込められてるように感じます。
日本銀行は昨年の12月19日に、政策金利を0.50%程度から0.75%程度へと引き上げることを決めました。2024年7月の0.25%、2025年1月の0.50%に続く、着実かつ確実な「金利のある世界」への歩みを進めています。
この12月25日の講演が、なぜ経営者にとって、見逃してはいけない決定的な転換点なのかを、私なりにまとめてみましたのでご一読下さい。
予測ではなく前提への「昇格」
経営者を含む我々ビジネスパーソンは、これまでに多くの「経済予測」を目にしてきたはずです。
かつては「来年の成長率は〇〇%だ」というのが主流でしたが、最近では「来年もインフレになる」「為替は円高になるかもしれない」といった話もよく目にするようになってきました。
しかし、今回の植田総裁の発言は、そうした話と次元が異なると私には感じられました。
日本銀行は、米国経済の下振れリスクは低下し、国内の企業収益も高い水準を維持していると判断し、その上で、2027年度にかけて物価上昇率が2%の目標と整合的な水準で推移する確度が高まったと明言しています。
そう、これは単なる予測ではなく「このシナリオに基づいて、私たちは淡々と金利を上げていく」という、政策運営の前提が確定したことを意味すると考えます。
植田総裁が確信したメカニズムの正体
植田総裁がここまで強気になれるのは何故と思われますか。
それは講演の資料、図表3で示された「賃金と物価の循環メカニズム」が、もはや一時的な現象ではないと確信できるようになったからではないでしょうか。
生産年齢人口の減少をはじめとする労働市場の構造変化が不可逆的であることを踏まえると、経済に大きな負のショックが生じない限り、労働需給は引き締まった状況が続き、賃金には上昇圧力がかかり続けることが見込まれます。
プラスの物価上昇率が続き、家計や企業の予想物価上昇率が高まりつつあるなか、賃金や仕入価格の上昇を販売価格に転嫁する動きも着実に広がってきています。
来年は、今年に続き、しっかりとした賃上げが実施される可能性が高く、企業の積極的な賃金設定行動が途切れるリスクは低いと考えています。
植田総裁の講演内容(抜粋)
植田総裁は、これまでのように過去の物価上昇を追いかける「バックワード・ルッキング」な賃上げではなく、将来の物価上昇を前提とした「フォワード・ルッキング」な賃上げへの変化さえ期待しています。
ご理解いただけますか?賃上げは前提なのです。物価上昇も前提なのです。今までの30年間は、物価も上がらず、賃上げをしなくても何とかなった、そんな過去の前提が崩れたのです。
「ゼロノルム」の世界には二度と戻らない
植田総裁の言葉の中で、経営者が最も重く受け止めるべき一節があります。
それは、賃金と物価がほとんど変化しない「ゼロノルム」の世界に戻る可能性は、大きく低下しているという指摘です。
ゼロノルム(Zero Norm)とは、賃金や物価がほとんど上がらない状態が当たり前、という日本経済に長年根付いた社会的な規範や通念を指します。
デフレ期の30年間、日本企業は「賃上げを抑制し、投資を先送りし、現預金を積み上げる」ことで生存を図ってきました。厳しい経営環境下では、それは一つの正解だったかもしれません。
しかし、緩やかな物価上昇が続く世界では、その戦略は「正解」から「緩やかな自殺」へと変わります。現預金の価値は実質的に目減りし、投資をしない企業の生産性は相対的に低下し続けるからです。
経営者に突きつけられた「新しい前提条件」
「そうはいっても、そんな急に変化は起きないだろう」と聞き流すのは簡単です。
しかし、日銀が政策金利を0.75%に上げ、さらなる利上げを予告している以上、経営をゲームとして捉えるのであれば、そのルールはすでに書き換えられています。
これからの経営において、賃上げは「余裕があればやるもの」ではなく、「優秀な人材を確保し、生産性を高め、金利上昇を上回るリターンを生むための必須の投資」という前提条件に変わったのです。
以下で過去を振り返りながら、ポイントを解説して参りたいと思います。
なぜ現預金の積み上げが必要だったのか
さて、植田総裁は昨年12月25日の講演の冒頭で、1990年代後半以降の日本企業の行動を振り返り、非常に重要な指摘をされています。
それは、当時の企業が賃上げや設備投資を抑制し、現預金を積み上げたことは、厳しい経営環境下において「必要なものだった」としたことです。
振り返ると、わが国経済がデフレに陥った1990 年代後半以降、企業は、雇用の安定を優先し、賃上げや設備投資を抑制してきました。当時の企業行動は、厳しい経営環境に直面するもとで、失業率の上昇を抑える効果があったほか、企業自身の財務体質の改善にとっても必要なものだったと思います。
植田総裁の講演内容(抜粋)
なぜ、当時は現預金を積み上げることが「経営の正解」だったのでしょうか。
そこには、日本特有の「デフレサバイバル」とも呼ぶべき3つの切実な理由がありました。
第一に、「雇用の安定」という重い社会的使命です。
1990年代後半の金融危機以降、日本経済は激しいデフレに飲み込まれました。この時、日本企業の経営者が最優先したのは、従業員の生活を守ること、つまり失業率の上昇を抑えることでした。解雇規制が厳しく、かつ「終身雇用」という無言の契約が残る中で、企業はいつ訪れるか分からない「最悪の事態」に備え、現金を「雇用維持のための保険」としてプールし続けなければならなかったのです。
第二に、「財務体質の改善(バランスシートの修復)」です。
バブル崩壊後の過剰債務に苦しんでいた企業にとって、利益を投資や賃上げに回す余裕などありませんでした。まずは負債を返し、現預金を積み上げて自己資本比率を高める。この「財務の健全化」こそが、当時の経営者にとっての至上命題であり、それが企業自身の頑健さを高める結果に繋がりました。
第三に、「デフレ下での経済的合理性」です。
物価が継続的に下落するデフレ下では、現金の価値は持っているだけで相対的に高まります。逆に、今日設備投資をすれば、明日にはその設備の価値が下がってしまう。将来の不確実性が極めて高い中で、投資を先送りし、現預金を積み上げるという行動は、当時の経済合理性に照らせば「最もリスクの低い、賢明な判断」だったのです。
この様に「動かないこと」が、かつての日本企業にとって生き残るための「最強の生存戦略」でありました。
日本企業を救った「3つの抑制」とその功罪
この「雇用の安定」「財務体質の改善」「現預金の積み上げ」という3つの行動は、確かに日本経済をどん底から救いました。倒産を回避し、雇用を守り抜いた功績は計り知れませんし、私自身も、それを行動規範として仕事をして参りました。
しかし問題は、この「成功体験」があまりに長く、あまりに強烈すぎたことです。約30年もの間、このサバイバルモードを続けた結果、経営者のDNAには「動かずに耐えれば、嵐は過ぎ去る」、「キャッシュこそが正義であり、投資はリスクである」という思考が深く刻み込まれてしまったのではないか、と思う節がでございます。
しかし今、起きているのは「一時的な嵐」ではなく、金利と物価が動き出す「大規模な気候変動」です。
かつての正解をなぞり、賃上げを渋り、現預金を抱え込んでいるだけでは、インフレによって実質的な資産価値は目減りし、優秀な人材から順番に、変化を受け入れた他社へと流出していくことになります。
植田総裁が「こうした状況を乗り越え、現在は人件費や設備投資が緩やかに増加するようになってきている」と述べた裏には、「しかし、その歩みは、過去の呪縛から解き放たれていないのではないか」という強い懸念が透けて見えます。
現在は、こうした状況を乗り越え、人件費や設備投資が緩やかに増加するようになってきています。もっとも、企業収益の大幅な増加に比べて、これらの伸びが相対的に緩やかなものにとどまっているとの指摘もあります。結果として、企業が生み出した付加価値の総額と人件費の関係を示す労働分配率は、緩やかな低下傾向が続いています。
植田総裁の講演内容(抜粋)
なぜ「設備投資の蛇口」は錆びついたままなのか
ここで、植田総裁が示したデータを確認してみましょう。
以下図表にある通り、日本企業の営業利益はこの10年余りで約2倍にまで増加しました。しかし、それに対して人件費や設備投資の伸びは、収益の増加に比べて驚くほど緩やかです。
左側の図表をご覧ください。
なぜ、これほどの利益がありながら、設備投資への蛇口は開かないのでしょうか。そこには3つの構造的な「心理的ブレーキ」が存在します。
「一時的な利益」への警戒感
経営者は、現在の高収益がインフレや円安、あるいは一時的な需要拡大によるものだと考えがちです。「来年はこの利益が剥落するかもしれない」という恐怖が、固定費である人件費の増額を躊躇させます。
不確実性への「現預金バッファ」信仰
デフレ期には、現預金を持っていること自体が実質的な価値の維持に繋がりました 。この「現預金こそが最強の防御」という信仰が、将来を見据えた「攻めの投資」への転換を阻んでいます。
「横並び」の安心感
「他社もまだ本格的な投資はしていない」「業界全体が様子見だ」という空気が、経営判断を「後出しジャンケン」へと誘導します。
デフレ期の習慣に従い、「今は特殊な状況だ。もう少し待てば、また以前のような安定(ゼロノルム)に戻るはずだ」という無意識の期待が、数億円の設備投資や数パーセントのベースアップという「決断」を阻んでいます。
しかし、植田総裁ははっきりと告げました。「ゼロノルムの世界に戻る可能性は、大きく低下している」と。
労働分配率の低下という「人材への出し渋り」
この「投資の抑制」の結果として現れているのが、労働分配率の低下です。
企業の利益が1995年比で200%を超える水準まで急拡大しているのに対し、人件費は100%をわずかに超えた程度で推移しています 。
その結果、分母(付加価値)の拡大に分子(人件費)が全く追いつかず、労働分配率は右肩下がりを続けているのです 。
右側の図表をご覧ください。
これは、企業が稼ぎ出した利益を、将来の成長の源泉である「人材」へと適切に還流させていないことを意味します。
デフレ期であれば「雇用の維持」が優先されましたが、現在は人手不足という供給制約が深刻化しています 。
この状況下で労働分配率を下げ続けること、つまり利益に見合った分配(賃上げ)を渋り続けることは、優秀な人材という「最大の資本」を他社へ流出させる、実質的な「経営の衰退」を招くのではないでしょうか。
植田総裁が突きつけた「ゼロノルム」の終焉
先ほども書きましましたが、植田総裁は、2%の「物価安定の目標」が持続的・安定的に実現する確度が高まっており、賃金と物価がほとんど変化しない「ゼロノルム」の世界に戻る可能性は大きく低下したと、断言しました 。
生産年齢人口の減少をはじめとする労働市場の構造変化が不可逆的であることを踏まえると、経済に大きな負のショックが生じない限り、労働需給は引き締まった状況が続き、賃金には上昇圧力がかかり続けることが見込まれます。また、プラスの物価上昇率が続き、家計や企業の予想物価上昇率が高まりつつあるなか、賃金や仕入価格の上昇を販売価格に転嫁する動きも着実に広がってきています。こうしたことから、賃金と物価がほとんど変化しないという、いわゆる「ゼロノルム」の世界に戻る可能性は、大きく低下していると考えています。
植田総裁の講演内容(抜粋)
デフレ期であれば、投資を先送りしても、現金の価値が目減りすることはありませんでした。
しかし、緩やかな物価上昇が続く世界では、投資をしないこと(現金を抱え込むこと)自体が、現金の価値を下落させ、企業の競争力を奪っていきます。つまり企業は「実質的な衰退」に入ります。
多くの経営者が動かない別の理由は「横並び」の安心感かもしれません。
「周りもまだ本格的には賃上げしていない」「業界全体が様子見だ」 そう思っているうちに、構造転換は遅れ、後で一気にツケが回ってきます。
植田総裁が「期待されるさらなる変化」として求めたのは、過去の成功体験という名の「ブレーキ」を外し、人への投資やAI・省力化投資という「アクセル」を強く踏むことなのではないでしょうか。
もはや「現状維持は衰退の始まり」という、経営者の皆さんであればご存じのビジネスティップスの通り、変わらないこと、現状維持に逃げることは、衰退へのカウントダウンの開始であることを認識する必要があるのかもしれません。
新年早々、重い話ではあるのですが、大きく環境が変化を時とは、言い換えればチャンスでもあります。私自身も評論家には絶対にならず、ビジネスパーソンのいちプレーヤーとして自己変革を続け、大変化の時代の荒波に乗ってみたいと考えています。皆様の思考の参考に、少しでもなれば幸いでございます。ご一読を頂きまして、ありがとうございました。
木﨑 利長
化学メーカーの住宅部門に約9年。1999年2月生命保険会社に、ライフプランナーとして参画。
具体的には、上場企業を含む約80社の親密取引先のご縁を中心に、生命保険契約をお預かりしており、財務や資金繰りといった経営課題ついての改善や、売上を伸ばすための営業研修など、お客様の事業価値を向上させるための具体的なソリューションを提供し、経営者の弱音をも受け止められる担当者を目指し日々精進中です。
(※このブログでの意見は全て個人の意見であり所属する団体の意見を代表するものではありません。)
最新記事 by 木﨑 利長 (全て見る)
- 日本銀行の金融政策から読み解く「経済の前提条件」の変更とは - 2026年1月11日
- 「金利のある世界」になり、金融機関の行動は変わりますよ - 2025年4月15日
- 社長の仕事である「経営」とは何かを、分かりやすく定義してみる - 2024年11月18日